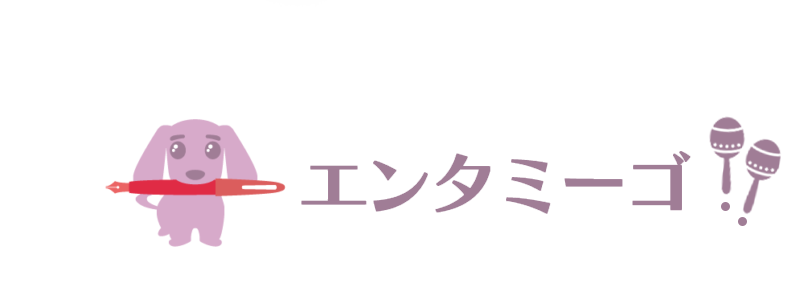主演:片岡礼子、脚本・監督:安田真奈、実験的短編映画『あした、授業参観いくから。』が、2022年4月16日(土)より新宿K’s cinemaにて上映される。
「あした、授業参観いくから。」「えっ…」7つのせりふが5つの家庭で繰り返され、全く同じ会話なのに異なる親子模様が描かれていく本作。2021年12月に大阪・シアターセブンで公開されたところ多くの反響が寄せられ、リピーターが続出。4回も追加上映された作品だ。
東京での上映を控え、脚本・監督を手掛けた安田真奈さんにインタビューを行った。本作にかける想いと自身のキャリアについてたっぷり語っていただいた。

今こそ家族について考えたくなる映画を作りたい
――23分の短編映画『あした、授業参観いくから。』を撮ろうと思ったきっかけは何ですか?
安田真奈(以下、安田):上野樹里さんと沢田研二さんの電器屋親子映画『幸福(しあわせ)のスイッチ』(2006年)の監督・脚本をつとめて以来、「家族」って大事なテーマだな…とずっと考えてきました。また、長年やっている脚本や演技のワークショップでは、「同じせりふでも、演技プランや脚本のト書きが変わることによって全然違うシーンになるよ」と説明しています。その二つが組み合わさって、同じせりふの繰り返しで、異なる家族像を描こう、と思いつきました。
そして家族について考えたくなる映画というのは、今の時代に必要だと考えました。家族の行動がバラバラになってきたり、子どもの考えていることが見えなかったり、コロナ禍で児童虐待が増えたり、親子関係に亀裂が入ったり…。社会全体で、親子を優しく見守らなければいけない時代に突入していると思います。
なぜ「あした、授業参観いくから。」というせりふにしたかというと、日本人であれば誰でも授業参観に何かしら思い出があるからです。
授業参観の前日、親と子で行くとか行かないとか話をするだろうし、その言葉を発した瞬間、親子の関係が浮き彫りになります。同じせりふでも脚本に落とし込んで映像化してみると伝わり方って違うとか、同じ教室にいて同じように見える生徒でも背負っている家庭環境は違うねという、さまざまな親子の想いを描くのにとてもいい素材だと考えました。
――本作をあえて23分という短編にした意図は何ですか?
安田:「全く同じせりふを繰り返す」という実験的な構造の作品なので、できればこのせりふだけで終わりたいという気持ちがありました。でもそれだけと伝わりづらいので、多少せりふを加えましたが、複雑な会話は入れていません。
観ている側の感覚として、同じ会話の繰り返しなら、せいぜい5家族ぐらいが観やすいだろうなと思いました。それに、同じ言葉をかけても関係性によって伝わり方が違うということを「実験的な構想」として活かすには、長い尺よりも短い尺で投げかけたほうが、想像の余地も生まれると考えました。

さまざまな事情がある5家族をセレクトした理由とは?
――短編だからこそ、じわっと余韻が残る作品になっていると私は感じました。中でも今の時代に問題となっている親子関係を描くかのように、いろいろな家族が登場します。こうした家族像を取り上げた意図はあったのでしょうか?
安田:作品に登場する5家族は、親が授業参観へ行くと言っているので、最低限子どもに対して愛情がある家庭なんです。でも愛情があっても表現がうまくいってなかったり、子どもに苦労をさせていたり、圧が強すぎて子どもが怯えていたり、本当にさまざまです。
子どもへの愛情はあるけれど、うまくいっている家庭とうまくいっていない家庭を描き分けると、観る方が「ああいうケースを見たことがある」「うちはこういうふうになっていないか」「うちはこうありたい」とか、自分の身の回りに重ね合わせられると思うんです。同じ言葉をかけるにしても、タイミングや声のかけ方、態度はすごく大事なんだな、と感じていただけますしね。



私は2011年にNHKで『やさしい花』という児童虐待をテーマにしたドラマの脚本を書きました。隣人の虐待を止められるかというテーマで、谷村美月さんと石野真子さんが熱演されています。その時に児童虐待についていろいろな方に取材をしましたし、上映と講演が続いているので、厳しい家庭のケースをお聞きすることが多いんです。
どんなに厳しい家庭でも、親は根底で、子どもをうまく愛したいと思っている。でも子どもからすると「そんなふうに思っているのなら、もっとちゃんとしてくれよ」という気持ちになる。幸せになりたくて子どもを育てているはずなのに、うまくいかない切なさがすごくあるんですよ。
こうした親をダメな親だと断罪するのではなく、周囲の人たちはいい感じに見守って手を差し伸べ、子育てを「見張る」のではなく「見守る」みたいな空気を作ることがすごく大事だと考えるようになりました。
この映画を観終わったあとは、「あの親はあかんかったな~。許されへんわ」ではなくて「あのお父さんは、子どもを思っている気持ちは分かるけど、あれはあかんよな」「あのお母さんは家事をほったらかしにしているけど、もしかしたら娘のことをすごく自慢に思っているかもしれへんな」というふうに、批判だけでなく胸の内を想像するなど、建設的な話もしていただけたらなぁと思います。
ある観客の方がおっしゃっていたんですが、5家族の中の一つに、一見理想的な家庭も登場するのですが「あの家庭も何があるか分からないよ」と(笑)。
私はよく映画の中で、「人というのは、見たままではなくさまざまな事情を背負っている」ということを描いています。本作でも、そういうことに興味を持つ、想いを馳せる、見守る気持ちが生まれるような作品にしたいと思いました。
現場を明るく元気に盛り上げる主演・片岡礼子

――片岡礼子さんが、学校の先生役を演じています。生徒と関わるシーンが少ないだけに難しい役どころだったと思いますが、印象はいかがでしたか?
安田:素晴らしい方でした。圧倒的にリアリティーのある芝居をしてくださる方なんです。3日間の撮影で、2日お越しいただいたんですが、ものすごく現場を明るく元気に盛り上げてくださいました。
撮影が終わってからも「スタッフキャストリストをください。またいつかご一緒できるときがあるかもしれないから、お名前を把握しておきたいです」とおっしゃってくださって…。なかなかベテランの俳優さんが言えることではないので、キャスト、スタッフのみんなでジーンと感動しました。演技が素晴らしいだけでなく、とても情に厚い方なので、本当にご一緒できてよかったです。

――片岡さんは、先生役なのに生徒とのからみがほんどないので、シナリオを読んだ時はちょっと戸惑ったようですが…。
安田:この映画は学園ものではなくて、親子ものなんです。ですので、先生が生徒と関わるシーンもそんなにないし、いろいろな親子を点描していきます。親もかつては子どもであった。親はずっと親である、子はずっと子である…。「親子とは?」が軸になっている作品です。
物語の中で、いじめにあっている子どもが出てきますが「このいじめは解決されるのか!」と追求する学園ドラマではなく、瞬間、瞬間で家庭の親子像を切り取って、あなたが近いのは誰でしょう? 見守りたいのは誰でしょう? どの親子像から何を感じますか? というように、親子関係について考える映画です。さまざまな親子をふわりと優しく見守る気持ちになっていただけたら嬉しいです。
森田芳光監督の『家族ゲーム』をきっかけに日常を描く映画を作りたいと思うように
――映画監督を目指したきっかけは何ですか?
安田:ものすごく映画を観ていたり、小説をすごく読んでいた文学少女というわけではありませんでした。若い頃、映画というものは美男美女の恋物語や、SFなどのスペクタクル感があるものだ、非現実的な世界だ! と思っていたのです。
ところが高校に入る頃、たまたまテレビで、松田優作さんが主演をされた、森田芳光監督の『家族ゲーム』を観て、日常的な設定からもこんなに面白い映画が作れるんだと衝撃を受けたのです。中流家庭に家庭教師が来るだけの話なんですけど、同じ屋根の下にいるのに家族に距離感がある雰囲気を、横一列の食卓で表していたり…。
その時に、監督が「こんな雰囲気で行こう」と役者やスタッフをリードするんだな、そしてベースにオモシロイ脚本があるんだなと知り、監督と脚本というパートに興味を持ちました。すぐに高校の映画研究部に入りましたが、自分の作品はなく、みんなでワイワイ撮って遊んでいた感じです。
――大学時代に映画サークルに入っていたそうですが、どんな作品を撮っていたのですか?
安田:大学のサークルでは、アクションを撮っている先輩やギャグやドラマを撮っている先輩など、いろいろな方がいましたので「なんでも撮ってええよ」という雰囲気でした。
ですから、最初は一発ギャグを撮ったりしていました(笑)。もしも芸術大学などで映画のことを学んでいたら、ドラマなどの本格的な作品からスタートしていたかもしれないのですが、逆に専門的に学んでいないからこそ、怖いものがなかったんですよ。下手でも誰にも怒られませんから。
気楽にバンバン気にせずに撮っていったことが、自分にとって良い経験になりました。3分~5分ほどの軽いものをサクサク撮っているうちに、自分なりに得意なジャンルが分かってきました。
会社員時代も映画を作り続け、バイタリティーあふれる手法でアピール
――大学卒業後は、映画の道に進まず会社員になったんですよね。
安田:大学4年になる頃には、30分くらいのドラマを撮ったりしていたので、映画の世界も面白そうやなと思っていました。
NHKで放送するドラマは落ち着いたトーンで好きだったので、テレビ局はNHKだけを受けて落ちました。華やかな世界に行きたかったわけではないし、テレビの仕事は忙しくて自分の時間を持てないだろうから、放送業界に未練はありませんでした。
大学時代、映画サークルの他にもう一つ企画のサークルに所属していました。当時は広告が全盛期だったので、CMプランナーになりたいと思っていた時期もあったのです。大学にコラムニストの天野祐吉さんをお招きして「自分たちが生きてきた20年間を、コマーシャルを見ながら振り返る」という講演会を企画したりしました。
その流れで広告の会社も受けましたが、狭き門でしたね。私は根本的にモノづくりが好きなんで、多く受けたのはメーカーです。みんなでモノを作って、それがどのような反響をうむか…ということに興味があったので。最終的に、家電メーカーに入社しました。
――会社員時代は、どんなことをなさっていたのですか?
安田:松下電器産業(現:パナソニック)の家電本部で、地域電器専門店の販売促進の仕事をしていました。派手なマスコミ宣伝ではなく、電器屋さんが使うチラシ、カタログの発行や、展示会の企画推進といった、地味な仕事です。1993年に入社して、2002年9月まで9年半勤務しました。
映画については、働きながら自主制作で撮って、各地の映画祭に応募していました。当時は、まだ女性監督が少なかったし、映画の中心は東京でした。
女性で、地方在住、なおかつ他の業種の正社員をしていると「本気で映像をやる気はない」と思われてしまう、ちょっとした三重苦状態でした。でも、映画祭に行った時、「大阪から来ました! 今は他の業種で仕事をしていますが、いつか映像の仕事をしたいです!」とアピールすれば、覚えてもらえるな、と気付きました。
そして、手裏剣のようにいろいろな方に名刺を配って(笑)手裏剣名刺が刺さった人には、プロフィールやVHSもお渡しする…ということを地道に行っていました。
でも、プロデューサーの方々はお忙しい方がほとんどです。「最初の5分だけでも見てください!」と、冒頭に予告編をいれたVHSビデオを渡したりしました。映画のCMによく使われている手法ですが、上映会に来られたお客さんの「感動しました」「友達に会いたくなりました」などといった感想コメントを予告編に足して、「安田真奈は、世の中に受け入れられている作家だ」と印象がつくようにしたのです。
不利だと思っていた、大阪在住であることも、時には利用できました。東京へ行く機会があればプロデューサーに「今度東京にいくので、事務所にお邪魔していいですか?映画祭ではゆっくりお話しできなかったので…」と連絡をとりました。プロデューサーは基本的に面倒見のよいので、会ってくださいます。先方がどんな作品や作家を求めているのか、こちらがどんな企画を考えているのか、情報交換して、「いつか映像の仕事を始めたらぜひお願いします」と話しました。
関西テレビの番組として、2000年『オーライ』、2001年『ひとしずくの魔法』を撮ると、脚本の依頼なども増えてきたので、「さすがに正社員の仕事と映画の両立は難しいかな」と思い、会社を退職しました。
「映画監督になろう!」そう決心した時に決めたマイルール
――監督はバイタリティーがありますね!
安田:地道な販促の仕事をやっていた経験はとても大きく活きていると思います。私は、誰もがオファーしたくなるような飛びぬけたセンスは持ってないので、「皆さんと一緒にお仕事ができるように頑張ります!」という感じでやっています。
「いつか映画監督としてやっていきたい」という気持ちが芽生えたのは、社会人2年目以降。自主映画が映画祭で受賞し始めてからです。そこからは、働きながら作り続けるために、マイルールを4つ作りました。
一つ目は、年に1本は短くてもいいから映画を作る。作って発信するたびに出会いがありますし、たくさん作れば少しは上達するかもしれません。
二つ目はあるものでなんとかする。構想が壮大だと何年も撮影に着手できなかったりするけど、例えば「このコップがキレイ」と思ったら、それで脚本を書いて来月撮る、ぐらいの軽いフットワークで。そうすれば、年1本撮れますしね。この「あるものでなんとか」書いていた経験が、後の脚本仕事に活きました。仕事ではいろいろな条件を課せられることが多いんですが、どんなお題や条件がきても怖くなくなりました。
三つ目は宣伝する。自主製作は自分が宣伝するしかないので。
四つ目はサイクルを作る。作ったら必ず上映して、アンケートをとって、キャストやスタッフに共有するということ。そうすると、また助けてもらえますし、自分自身も何がウケて何がウケなかったか、検証できますから。
――今後はどのような作品を撮っていきたいですか?
すでに脚本が出来上がっているものが3つあります。
一つは、『虹色のネジ』。私はあまり光が当たっていないものに光を当てるのが好きで、地味なネジに惹かれるんです。ロボットやロケットがすごい発明といわれるけれど、ネジがなかったら全部バラバラですよね。ネジって縁の下の力持ちですし、モノとモノをつなぐというのがドラマのモチーフになる。ネジ工場を舞台に、おじいちゃん、お父さん、息子の男三世代の子育て物語を描きたいです。実は、劇中に登場する絵本「にじいろのネジ」はすでに出版してるんです。はりたつおさんに絵を描いていただき、私は文を担当しました。
もう一つは『胎内の魚』。これは母と娘の愛憎物語です。世の中には、虐待まではいかないけど、お母さんの考えに従ってしんどい女の子ってめちゃくちゃ多いと思うんです。そういう人が観たら、何かしらの気付きがある、ちょっと心が楽になる映画です。
そしてもう一つは、繁華街をさまよっている行き場のない女の子の物語。
この3つの脚本を用意して、映像化の機会を狙っています(笑)。
いろいろな世代に人に楽しんでもらいたい『あした、授業参観いくから。』
――『あした、授業参観いくから。』はどのような人に観てほしいですか?
安田:大阪のシアターセブンで公開した時に、300枚以上の熱い感想メモが寄せられました。ご年配の方からは「かつて娘の参観に行ったことを思い出して、胸が熱くなりました」という感想をいただき、若い方からは「同じせりふなのに、全然違う感じに表現されていて面白かった」という感想をいただきました。
この作品は、「授業参観」という誰にでも思い入れのあるテーマなので、それぞれの世代で楽しめるんです。親子で観ることができる映画ですし、短い時間で観られるから誘いやすい。実際に「先週は一人で来たけど、今日は娘と来ました」という親子で来場される方も少なくありませんでした。
観たあとに「あの親子どうなんだろうね」「うちみたいだったね」などと話が弾みますし、世代を選ばず、いろいろな方々に観ていただける作品だと思っています。
――改めて作品のアピールをお願いいたします。
安田:短編ならではの観やすさ、実験的な構造の面白さがあるので、何回も観てくださるかたがいらっしゃいます。観るたびに、演技や映像や音など、いろいろな発見があるそうです。
映画をあまり見ない小学生や中高生の方にも、見ていただきたいですね。身近なせりふの映画ですし、「同じせりふでも映像がこんなに変わるんや」と、映画づくりの面白さに気づくきっかけになるかもしれませんから。ぜひ、たくさんの方にご覧いただきたいなと思っています。
取材・文:咲田真菜
安田真奈 プロフィール
映画監督・脚本家。シナリオ作家協会所属。メーカー勤務約10年の後、2006年、上野樹里×沢田研二の電器屋親子映画「幸福(しあわせ)のスイッチ」監督・脚本で劇場デビュー。同作品で第16回日本映画批評家大賞特別女性監督賞、第2回おおさかシネマフェスティバル脚本賞を受賞。同年末に出産後は脚本業中心となったが、2017年より監督業復帰。堀田真由主演映画「36.8℃ サンジュウロクドハチブ」、小芝風花主演の近大マグロの青春映画「TUNAガール」の監督・脚本をつとめた。
安田真奈 公式サイト https://yasudamana.com/jp/
映画『あした、授業参観いくから。』作品情報

2022年4月16日(土)〜4月22日(金)新宿K’s cinemaにて1週間限定公開。
期間中トークを予定しております。
会場:新宿K’s cinema 東京都新宿区新宿3丁目35-13 3F
TEL:03-3352-2471 FAX:03-3352-2472
連日12:00〜 料金:1000円
上映詳細は新宿K’s cinemaにて
https://www.ks-cinema.com
短編映画「あした、授業参観いくから。」作品詳細は下記サイトにて
http://www.parasang.co.jp/works/index.html#movie
■名古屋アンコール上映! シアターカフェ2022年4月30日~5月6日 火曜水曜定休
愛知県名古屋市東区白壁4-9 https://theatercafe.jp/new/
【出演】
片岡 礼子
和泉 敬子 前田 晃男
上本 康義 島田 愛梨珠 楠 葉子 塚原 健司 坪内 花菜 河﨑 公一 下松谷 嘉音 森 琴樺 内藤 大帆 佐野 亮華
成瀬 千尋 長三 伊乃 歳内 王太 荒木 隆一 ほか
【スタッフ】
脚本・監督:安田 真奈 プロデューサー:山本 祥生 撮影:武村 敏弘 j.s.c 照明:古川 昌輝 音楽:原 夕輝 録音:小出 佳史
助監督:柳 裕章 メイク・スタイリスト:谷山 伸子 美術:山中 昭子 宣伝・予告編編集・WEBサイト:三島 彩香
編集:藤沢 和貴 ミキサー:岩田 修一 制作:船津 春菜 製作:株式会社パラサング